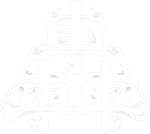>>ルール動画
>>競技概要
パスを使ってゴールマンにボールを渡して得点する競技
>>基本情報
- 試合時間:
- 中学: 計9分(前後半 各4分、ハーフタイム1分)
- ⾼校: 計13分(前後半 各6分、ハーフタイム1分)
- 終了条件: ブザーが鳴り終わった時点のプレーが切れた瞬間
- 勝利条件: 前後半の合計得点が⾼い⽅
- 競技⼈数: 前後半各6⼈‧計12⼈(前後半総⼊れ替え)。6⼈の内2⼈は、ゴールマン(カゴ役の⼈)と、ガードマン(ガードゾーン内でのディフェンスをする)
- ⼈数調整: ⼈数の多い側のチームが相⼿の前後半の両⽅出場する選⼿を指名する
- 試合会場: グラウンドの外野(ボールはバレーボールを使⽤する)
>>競技規則
<試合進⾏>
- 試合開始: 両チームから1⼈づつがコートの中心に⽴ち、じゃんけんで試合をスタートする
- 試合時間: 前半後半で6分づつとし、それぞれで選⼿は総⼊れ替えとする
- ⽬的: プレイヤーはパスを⽤いてゴールマンにボールを渡し、得点することを⽬的とする
- 勝敗決定: ゴールを1点とし、前後半合わせて合計点数が多いチームを勝利とする
<基本ルール>
チーム構成とポジション
- 1チームは6⼈で構成される
- ボールはバレーボールを使⽤する
- 各チームには、以下の3つのポジションが存在する(このポジションは⼀試合を通して固定とする)
- ゴールマン(1⼈): ゴールゾーン内にいて、味⽅からのボールをキャッチして得点を狙う
※ゴールゾーン外には出てはならない
- ガードマン(1⼈): ガードゾーン内にいて、ゴールマンがキャッチできないようにディフェンスをする
※ガードゾーン外(ゴールゾーンを除く)にいても反則ではない
- フィールドマン(4⼈): ボールをパスで運び、攻撃を⾏う
※フィールドマンは、ガードゾーンおよびゴールゾーン内に⼊ってはならない
- ゴールマン(1⼈): ゴールゾーン内にいて、味⽅からのボールをキャッチして得点を狙う
得点⽅法
- ゴールマンが味⽅からのボールをキャッチすると1点を与える
得点したときの再開⽅法
- 点が⼊った場合は、点を⼊れられたチームのガードマンが、エンドラインからパススタートとする。
- ゴールマンがボールを渡さないなど、遅延⾏為と認められるものがあった場合、減点の対象となる
<反則、ペナルティについて>
ボールの運び⽅についての反則
- ⾃分より前の⼈にパスをしても反則にはならない
- ボールを受け渡すときは、ボールが⼿から離れている時間がなければならない。
- ボールを持った状態で3歩以上歩いてはならない(トラベリング)
- ボールを5秒以上保持してはならない(オーバータイム)
- ドリブルは反則とする
- ボールを蹴ることは反則とする
- ボールを故意に⾜に当てられた場合は反則とならない
- ボールを持った状態でラインを⽚⾜越えている場合をラインアウトとする
- 上記の反則があった場合は、反則があった地点から、相⼿ボールで、パススタートで再開とする
- 再開時に、守備側の選⼿は攻撃側の選⼿から約2m程度後⽅に下がること(この距離は主審の⽬分量で判断する)
ゴールマンについての反則
- ゴールマンが、ワンバウンド以上したボールをレシーブしても、ゴールを認める。
- ゴール時またはゴール直後にゴールマンがゴールゾーンからラインアウトした場合、ゴールを認めず、ガードマンがエンドラインからパススタートとする。
ガードマンについての反則
- ガードマンがゴールマンのレシーブを妨害する動作の中でラインアウトした場合は、相⼿ボールで、コーナーからのパススタートとする。
※注意事項:ガードマンとゴールマンが両⽅ラインアウトした場合は、両⽅が反則をしなかったものとして判定を下す
ボールアウトについて
- サイドラインにボールを出した場合は、出した選⼿の相⼿チームから、出た地点で、パススタートとする。
- 攻撃側がエンドラインにボールを出した場合は、ガードマンが、エンドラインからパススタートとする
- 守備側がエンドラインにボールを出した場合は、相⼿ボールで、コーナーからパススタートとする
その際、ゴールマンへの直接のパスは認めない。
ファウルについて
- プレーヤー同士の接触は原則禁止とする。
- ファウルのペナルティについては、ファウルがあった地点から、相手チームのパススタートとする。
>>反スポーツマンシップ⾏為について
- スポーツマンシップに反する⾏為とは、ボールをパスでゴールマンに繋いでいくという趣旨に反する行為をさす。
- 例としては以下を列挙する。これらに近い行為も01における行為に含む。
- 時間稼ぎ(遅延行為)
- 消極的行動(前進する気が無い)
- わざとボールを他人に当てる
- 密集してボールを運ぶ
- スポーツマンシップに反する⾏為は、現場の審判団幹部の判断で減点‧退場‧組失格の対象とする場合がある